見直された新公益法人制度
令和7年4月から施行された新公益法人制度では、従来の厳格かつ硬直的だった財務規律が見直されました。これにより、公益法人が自律的かつ柔軟な資金運用を行えるよう制度が整備され、持続可能な事業運営が可能となります。
公益法人制度はこれまで、財務の健全性を担保するために厳格な規律を設けてきましたが、その反面、現実的な事業運営においては資金の使い勝手が悪く、柔軟な対応が困難でした。新制度では、収支の考え方や資金管理の方法が大幅に見直され、法人の自律的な財務運営が可能になります。
1. 収支規律の見直し:単年度から中期へ
これまでの制度では、公益目的事業で黒字が生じた場合、原則として2年以内に解消しなければならず、赤字との相殺も認められていませんでした。また、事業ごとの個別収支で均衡を図る必要があり、全体としての柔軟な運営が難しいという課題がありました。
新制度では、収支均衡の考え方が「中期的視点(最大5年間)」に改められ、赤字と黒字の通算が可能になりました。これにより、一時的な黒字や赤字に過度に反応せず、中長期的な事業計画に基づいた資金運用ができるようになります。また、収支均衡の判断も、事業単位ではなく、公益目的事業全体の収支で評価されるため、資源の最適配分がしやすくなります。
2. 積立資金の一元化:「公益充実資金」制度
従来は、将来の費用に備えて「特定費用準備資金」と「特定資産取得資金」という2種類の積立を行い、それぞれ個別に管理・運用する必要がありました。これは資金の流動性を損ね、実務上も煩雑でした。
新制度では、これらを統合し「公益充実資金」として一括管理する制度が導入されました。この制度により、積立資金の使途を事業環境の変化や経営判断に応じて柔軟に変更することが可能になり、より戦略的な資金活用が促されます。公益充実資金の使い道は、公益目的事業の拡充や新規事業への投資、施設整備など多様な目的に適用でき、事業の持続性と発展性を高める仕組みとなっています。
3. 遊休財産保有規制の緩和と予備財産の明確化
これまで、使途が未定の資産(いわゆる遊休財産)の保有上限は、当該年度の公益目的事業費と同額に制限されており、資産を長期的に保有することが難しい状況でした。新制度では、上限の基準を「直近5年間の平均公益目的事業費」とすることで、年度ごとの変動による影響を抑え、資産保有に一定の安定性を持たせています。
さらに、災害やパンデミック、経済変動といった予見困難な事態に備える「予備財産」の保有が正式に認められるようになります。法人がその必要性と保有額の算定根拠を説明し、公表することで、計画的かつ適切なリスク対応が制度上保障されます。この変更により、突発的な支出に対応できる余裕を持った財務運営が可能になります。
持続可能な事業運営への転換へ
これらの見直しは、単に制度を緩和するものではなく、法人の「説明責任」や「自律的経営」を前提とした構造改革です。短期的な財務数値にとらわれるのではなく、中期的・全体的な視点で公益活動を支える体制が制度として整えられます。法人は今後、透明性と説明責任を果たしながら、自らの判断でより柔軟かつ戦略的な財務運営を行うことが求められることになります。

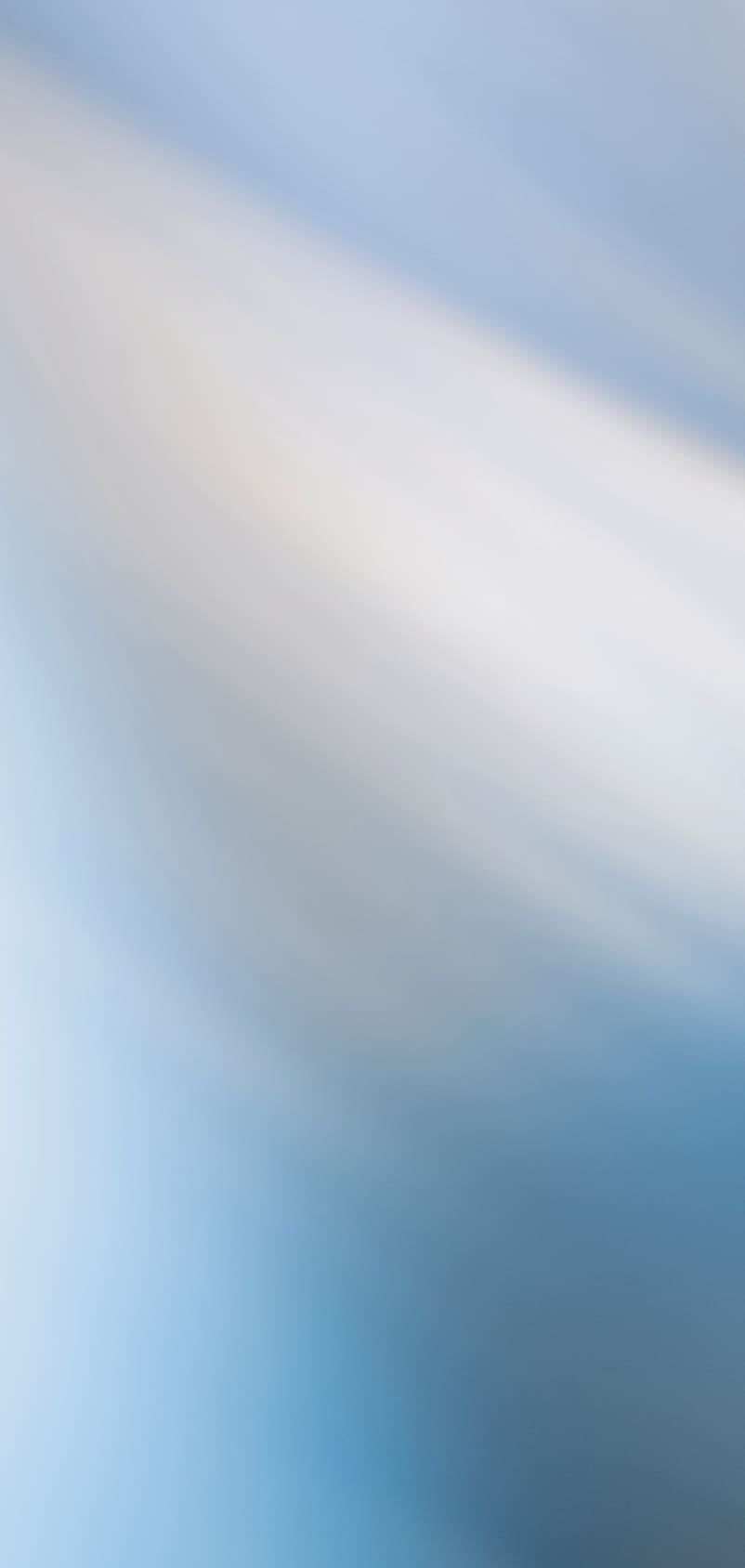


今年4月から施行された「新公益法人制度」をご存知でしょうか。従来の厳格かつ硬直的だった財務規律が見直され、自律的かつ柔軟な資金運用を行えるようになりました。
今回は、新公益法人制度についてお伝えしていきます。