制度設計の議論が本格化
政府の有識者検討会では、少子化対策推進の観点から出産費用制度の見直しについて議論を重ねてきました。来年度を目標時期として、出産費用無償化の実現に向けた詳細な制度設計を推進していくべきとする方針が示されています。
5月14日に実施された「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」では、2026年度を目標年度として標準的な出産費用における自己負担分の無償化実現に向けた制度設計を具体的に進めていく方向性が正式に決定されました。つまり、病気ではない正常な分娩についても公的医療保険の適用として、自己負担分を公費で支援するという方針です。
この方針決定により、厚生労働省は今後、無償化の対象範囲や実施手法などに関する具体的な制度設計作業に着手することとなります。
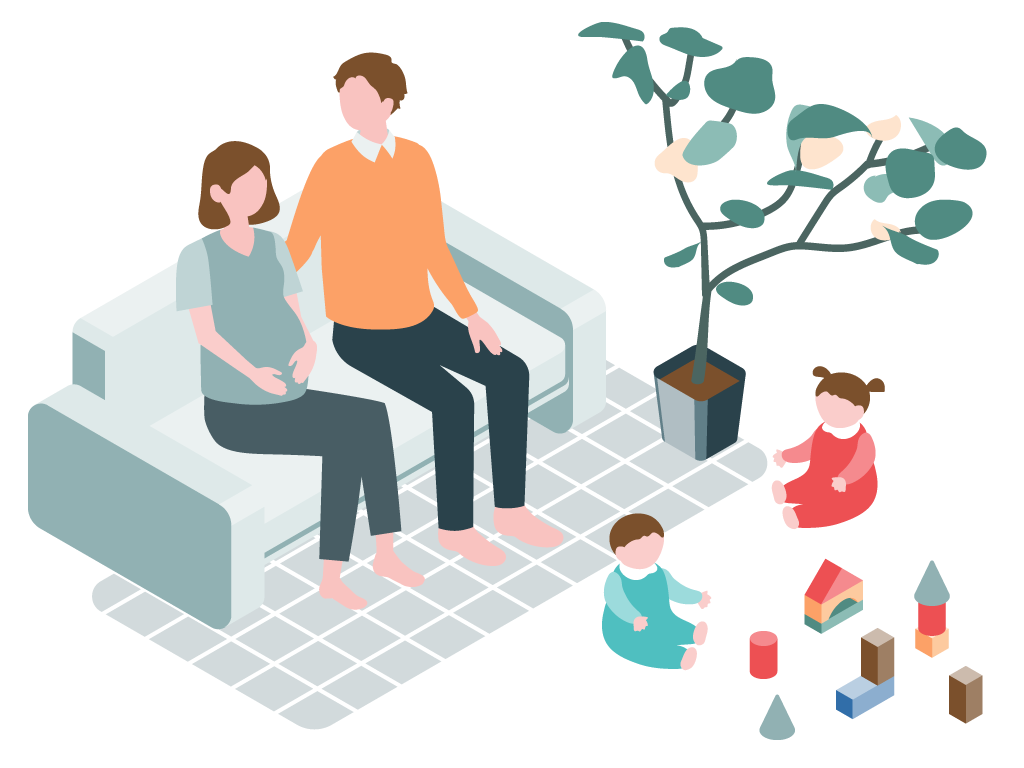
出産費用の実情、地域格差
現在、正常分娩にかかる費用は全国平均で増加を続けており、2024年度上半期には51万8000円程度となりました。50万円を突破した点にも注目が集まりますが、地域間の格差の大きさにも問題があります。最も費用の安い熊本県では38.9万円である一方、最も高額な東京都では62.5万円と、同じ国内でありながら1.6倍もの開きがあります。さらに、同一地域内でも医療機関による格差が存在し、費用のばらつきは顕著な状況です。
現行制度では正常分娩は保険適用の対象外となっており、その代替措置として出産育児一時金50万円が支給されています。しかし、実際の出産費用がこの金額を上回るケースが珍しくない状況となっています。上記の地域格差の実情からも、特に都市部などで妊産婦の経済的負担が大きくなっている状況が見て取れます。
産科クリニックの経営
分娩を扱う産科クリニックの経営環境は年を追うごとに厳しさを増しています。日本産婦人科医会が実施した調査結果によると、赤字経営となっている産科診療所の比率は、2022年度の41.9%から2023年度には42.4%へと上昇し、4割を超える深刻な状況となりました。新方針の導入に際しては、このような厳しい経営実態に対する十分な配慮が求められています。
医療現場からは「緊急時への対応体制を整備するには相当な投資が必要となる」「保険適用により収入が減少するのではないか」といった不安の声が寄せられており、また、地域の実情を無視した全国統一の診療報酬では運営が困難になるとして柔軟な制度設計も求められています。
費用の透明化
現在、出産にかかる費用には、医療上必要不可欠な診療費用と妊産婦が希望に応じて選択するサービス費用(お祝い膳やエステティックサービスなど)が混在している状況です。
しかし現状では、これらの費用内訳が明確に示されておらず、妊婦が必要なサービスを適切に選択できない環境にあることが調査で明らかになっています。
課題解決に向けて、各医療機関のサービス内容と費用情報を公開するウェブサイト「出産なび」を活用した情報の”見える化”を推進することも提言されました。
制度設計における基本原則と課題
検討会での論点整理において、新制度設計の基本原則として以下の2つの要素を両立させることが示されています:
- 標準的な出産費用の自己負担無償化(費用の透明化が前提)
- 安全性と質の高い周産期医療提供体制の維持・確保
さらに、診療報酬制度における適切な評価体系の構築や、医療安全体制の確保に向けた評価方法についても、今後の重要な検討課題として位置づけられています。
まとめ
出産費用制度の見直しは、妊産婦の経済的負担を軽減する重要な施策です。しかし一方で、産科クリニックの経営や診療提供体制にも大きな変化をもたらす可能性があります。今後の政策動向についても、引き続き注視が必要です。
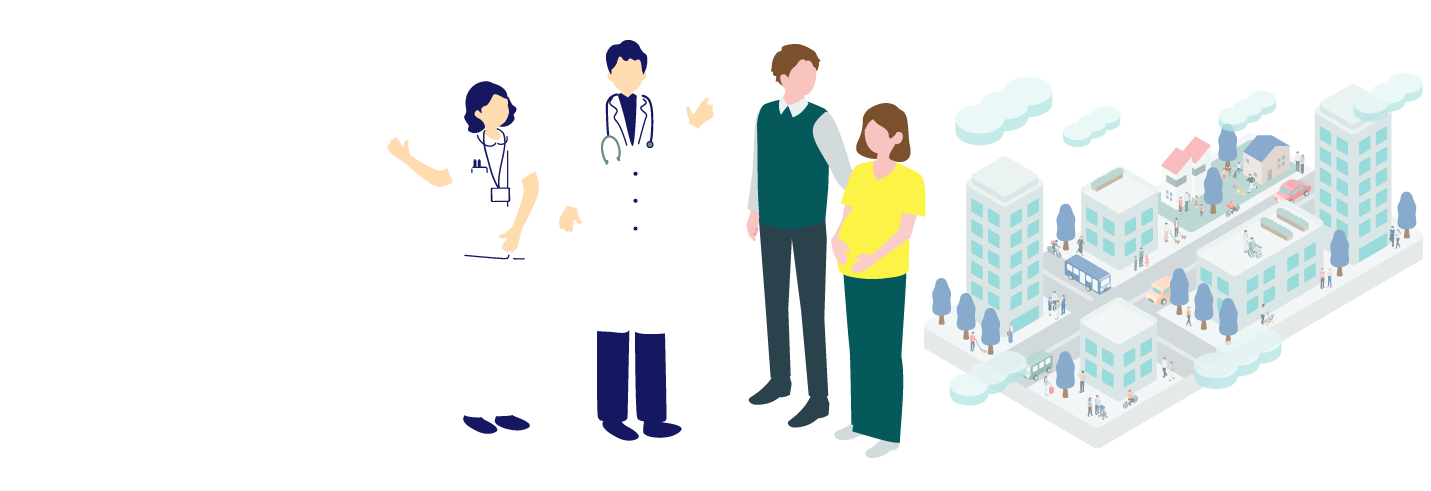

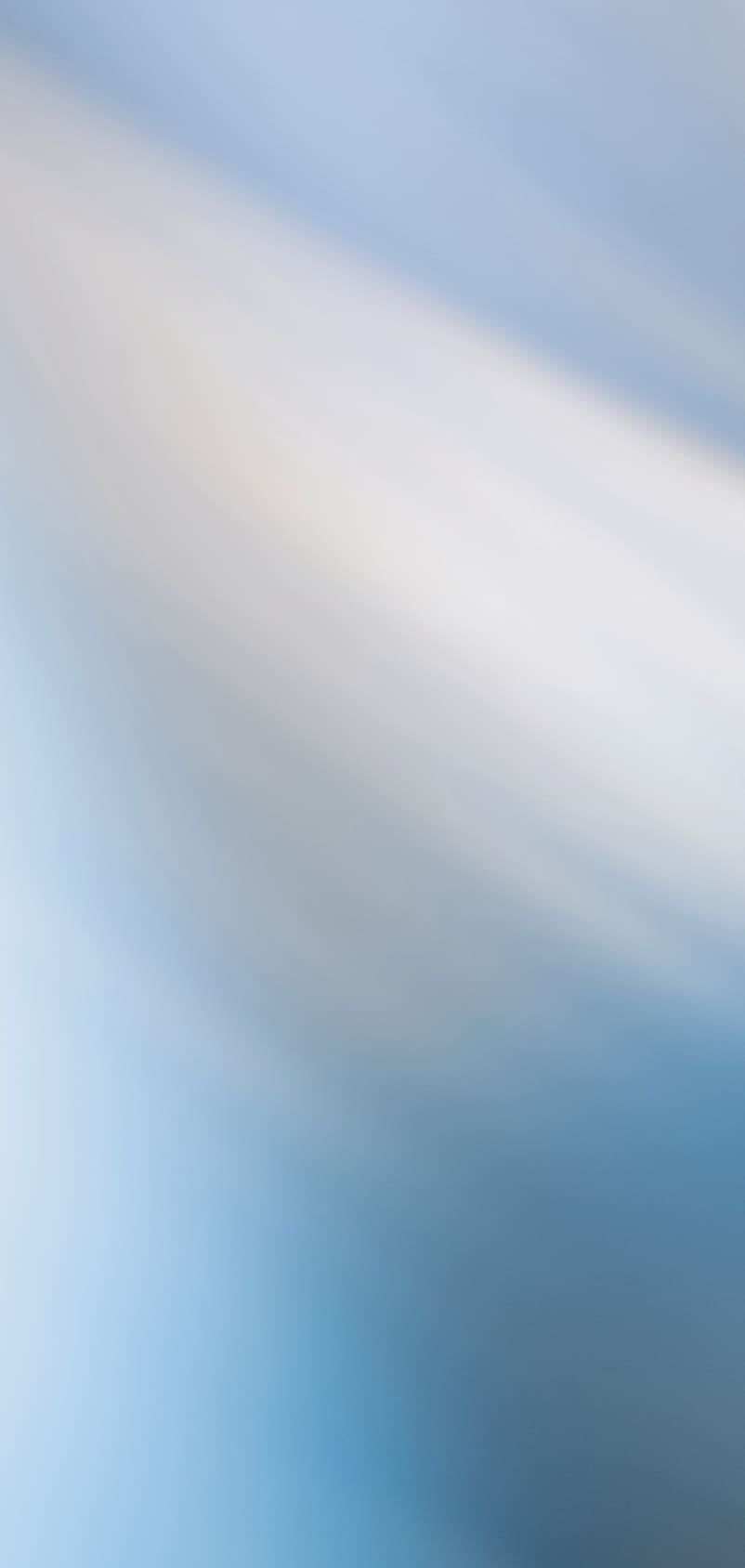


厚生労働省は、2026年度を目途に、出産費用の自己負担を原則無償化する方針を固めました。これは、正常分娩における自己負担をなくすことを目指すもので、経済的な理由で出産をためらう家庭を支援し、出生率の向上を図ることが期待されています。今回は、「出産費用の自己負担無償化」の動向についてお伝えします。